死ぬこと、生きること(第10号)-救いは恵み:人間の努力やがんばりは、一切関係ない
- TOP
- 死ぬこと、生きること(第10号)-救いは恵み:人間の努力やがんばりは、一切関係ない
死ぬこと、生きること(第10号)-救いは恵み:人間の努力やがんばりは、一切関係ない2024.12.19
救いは信仰によって、自分の意志や努力ではない
8月には『死ぬこと、生きること(第8号)-イエス様の十字架の死と復活は、私のためであった!』をお送りしましたが、読んで下さった皆さんは、次のように思うのではないでしょうか。講演でもよく頂くご質問なのですが、「吉田が、イエス様の十字架は、私のためであった、ということがわかったのは、東京神学大学の聴講生になるなど努力したからだ」と。私の答えは、否!!です。私の努力やがんばりは、一切関係ありません!
聖書は次のように言います。「従って、これは、人の意志や努力ではなく、神の憐れみによるものです。」(ローマの信徒への手紙9:16)、「事実、あなたがたは、恵みにより、信仰によって救われました。このことは、自らの力によるのではなく、神の賜物です。」(エフェソの信徒への手紙2:8)、「聖霊によらなければ、だれも「イエスは主である」とは言えないのです。」(コリントの信徒への手紙一12:3)
と言われても、何かを獲得するためには、がんばらなければならない、というのが、私たちの日常に染みついている考えと思います。ここから抜けられないんですね。
人の命は、財産によってどうすることもできない
ルカによる福音書(以下、「ルカ」と記載)12:15-21から引用します。
「「どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。」それから、イエスはたとえを話された。「ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、『どうしよう。作物をしまっておく場所がない』と思い巡らしたが、やがて言った。『こうしよう。倉を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。「さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ」と。』しかし神は、『愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意した物は、いったいだれのものになるのか』と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ。」」(ルカ12:15-21)
「人の命は財産によってどうすることもできない」とあります。ちょっと考えればすぐにわかることですよね。口語訳聖書では、「財産」は「持ち物」と訳されています。「財産」「持ち物」とは、お金や不動産、自動車といったものだけではなく、学歴や資格、才能、業績、プライド、自分を誇ることができる様々なもの、自分を安心させたり、支えたり、救われるために獲得し所有しているすべてのものを指します。
持ち物によって、自分のプライドを支えようとする惨め
夜もかなり遅い時間、駅前の塾から多くの子供たちが出てくるという場面をよく目にします。受験勉強、がんばっているんですね。親からはよい学校に行き、よい仕事に就きなさい、と言われているのでしょう。
日本よりも受験競争が激しい韓国でのこと、政府が医学部の定員を大幅に増やすことを決めたのをうけて、専攻医(日本の研修医)が一斉に病院を辞めてしまったというニュースは、ご存知の方も少なくないと思います。表向きの理由は、収入が減ることに対する不満と報じられています。しかし、2024年10月10日の読売新聞(朝刊)は、韓国のある病院長の言葉を載せています。「専攻医が病院を辞めたのはプライドの問題。これは深刻。自分たちは、がんばって、厳しい競争の中で医学部に合格した。それなのに、定員が増えると、競争は緩やかになりレベルが下がる。そんなことは絶対に耐えられない」のだそうです。
私は、目が点になりました。韓国の場合、病院の医師の4割が専攻医とのこと。報道によると、この騒動により、韓国の医療は崩壊寸前で、多くの患者さんが影響を受け、中には亡くなった患者さんもいるそうです。そんなことまでしないと、プライドが保たれないんですね。惨めな人たちですよね。常に自分を他人と比較して上だの下だの。何のために医者になったのでしょうか。きつい言い方かもしれませんが、箸にも棒にもかからない連中、と言いたいです。がんばって何かを獲得して生きることの一側面が現れていると思います。
この医者たちの姿、程度の差はあると思いますが、すべての人間の姿が現れていると思います。
何かを為すことにより、救われようとする愚か
努力したりがんばって、何かを獲得したり所有したり貯め込むことにより、安心したい、救われたいと願う人は多いと思います。そんなことをしても無駄だと薄々わかっていても、獲得したり貯め込もうとするんですね。しかし、神様はそういう人たちに向かって「愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意した物は、いったいだれのものになるのか」(ルカ12:20)と言われます。何かを為すことにより救われる、そんなことは絶対にあり得ない!です。
次は、がんばって律法を守り、自分の努力や正しさによって救われようとするファリサイ派の人と自分の内に誇ることができるものを何も持たない徴税人のお話です。
ルカ18:9-14です。
「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次のたとえを話された。「二人の人が祈るために神殿に上った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。『神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています。』ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。『神様、罪人のわたしを憐れんでください。』言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」」(ルカ18:9-14)
イエス様がおられるところに、しばしば、ファリサイ派の人々が付きまとっていました。彼らは、イエス様の命を付け狙っていたのです。ある律法の専門家(ファリサイ派の人)が、イエス様を試そうとして次のように言いました。「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」(ルカ10:25)何をしたら救われるのでしょうか、という質問ですね。残念ながら「何をしたら・・」と問う時点でもう終っています。
ファリサイ派とはどのような人々だったのでしょうか。彼らは、人に見てもらおうと目立つ場所を選んでお祈りします(マタイ6:5)。【自分】のがんばりを人に見せびらかして、敬虔な人、立派な人と褒められたいのです。また、【自分】の努力やがんばりで律法をガチガチに守っているような気になって、【自分】の正しさで、救いに至ろうとする人々でもあります。律法の研究に余念がなく、お勉強のできるまじめな優等生。【自分】、【自分】・・。ファリサイ派の人の【自分】は肥大し、かたくなになり、神様から離れてしまっています(根源的な罪)。イエス様から見れば「愚か者」(ルカ12:20)、「偽善者」(マタイ6:5)。箸にも棒にもかからない連中。【自分】に関しては『死ぬこと、生きること(第7号)と(第9号)』を参照して下さい。
ルカ18:9-14に戻りましょう。そのファリサイ派の人は、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下していました。彼らは、こんな奴らのような者ではない、この徴税人のような者でもないことを感謝します、と自信満々で祈っています。皆さんも思うんじゃないですか。「あんな連中ではなくてよかった」「あの人は素晴らしい、それに比べて自分は、何であんな奴が(妬み)」自分を他人と比較して上だの下だのと。常に自分のプライドを他人と比べてああだこうだと。『死ぬこと、生きること(第6号)-罪と死』の内容を思い出しますよね。
努力やがんばりで律法を守ることはできない
ここで、律法の理解を助けるためにひと言。人間がいくら努力しても、がんばっても律法を守ることはできません。ファリサイ派の人々は、神様に立ち帰ることなく、がんばって律法を守るという自分の正しさによって、救いに至ることができると思い込んでいますが、それは的外れ。罪です。「律法を実行することによっては、だれ一人神の前で義とされないからです。」(ローマの信徒への手紙3:20)とある通りです。
律法を守って救われる、ファリサイ派の人には、そんなことを言う資格さえ無かったと私は思います。パウロはユダヤ人に言うのです。「あなたは他人には教えながら、自分には教えないのですか。「盗むな」と説きながら、盗むのですか。「姦淫するな」と言いながら、姦淫を行うのですか。偶像を忌み嫌いながら、神殿を荒らすのですか。あなたは律法を誇りとしながら、律法を破って神を侮っている。」(ローマの信徒への手紙2:21-23)とどのつまりは、神様を蔑ろにし、他人との比較の中に生き、上だの下だのと常に言っている人たち。これがファリサイ派をはじめとするユダヤ人の姿だったのです。
ファリサイ派の人、酷いよね、と思われた方も少なくないと思います。でも、ちょっと待って下さい。ファリサイ派の人というのは、すべての人間のことです。ファリサイ派の人の【自分】は、アダムの【自分】と同じであり、全ての人間の【自分】なのです。ここでしっかりと確認しておきたいです(『死ぬこと、生きること(第7号)-根源的な罪:神様に背く【自分】』参照)。
徴税人は、「神様、罪人のわたしを憐れんでください」と祈った
ルカ18:9-14に戻ります。もう一人の登場人物、徴税人とはどのような人たちでしょうか。彼らは、ローマ帝国から徴税という仕事を請け負っていました。彼らは、ローマから給料をもらっていたのではなく、強引な取り立てにより、税金に自分の取り分を上乗せして、自分の懐に入れていました。だから金持ちなんですね。しかし、同胞から税金をあくどく取り立てる彼らは、罪人の代表と思われており、激しく忌み嫌われ、だれからも相手にしてもらえませんでした。会堂(教会)からも完全に排除されていました。いや、彼らは、礼拝したり、祈る資格さえ無いと思っていたでしょう。どうせ俺なんか、無視され嘲られ、救いから漏れている。彼らにはいつも軽蔑や嘲りの眼差しが注がれていました。
祈りの場面です。ファリサイ派の人は、堂々と自信満々で祈りました。一方、この徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言いました。「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」と。聖書は、徴税人は「祈った」ではなく「言った」と書いています。徴税人は、絶望していて、祈りの態勢すらとれないのです。祈る資格さえ無いと思っていました。徴税人は、声を絞り出すように「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」と。
ある牧師は、「憐れんでください」と訳されている言葉は、実は珍しい言葉で、意を汲むなら次のように言えると述べます。「神様、私はご覧の通りの人間です。あなたから裁かれて当然です。しかし主よ、私は他にどこに行けるでしょうか。どこで生きられるでしょうか。他に行くところはありません。他に生きるところは、もうないのです。あなたに差し出すものさえ、もう何もありません。主よ、あなたが私の罪をぬぐってください。」イエス様、あなたのそばにいさせてください。イエス様は言われます。救われたのは「この徴税人であって、あのファリサイ派の人ではない」と。
「今日、救いがこの家を訪れた」幸いなるかな、徴税人ザアカイ
ルカ19:1-10です。
「イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザアカイという人がいた。この人は徴税人の頭で、金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それで、イエスを見るために、走って先回りし、いちじく桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。「ザアカイ、急いで降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。」ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。「あの人は罪深い男のところに行って宿をとった。」しかし、ザアカイは立ち上がって、主に言った。「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。また、だれかから何かだまし取っていたら、それを四倍にして返します。」イエスは言われた。「今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は、失われたものを捜して救うために来たのである。」(ルカ19:1-10)
実は、この頃、徴税人や罪人たちはイエス様を訪ねるようになっていたのです。「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。」(ルカ15:1)とあります。徴税人の頭、ザアカイもその一人です。
ザアカイは、自分に絶望していたのです。彼は、いくらお金があっても「人の命は財産によらない」(ルカ12:15)ことを痛いほどわかっていました。上述の徴税人のように「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」と祈っていたでしょう。だからこそ、彼は、イエス様に少しでも近づきたかったのです。「自分の中のどこを見ても自分を支えられるものは何もない。空っぽ、もう、このお方だけ」
ザアカイは、イエス様に近づきたかったのですが、群衆に遮られて、近づけませんでした。嫌われ者のザアカイのために道をあけてくれる人は誰もいませんでした。それどころか、群衆が悪ふざけをして、絶対に近づけないようにしたのです。そこで、ザアカイはイエス様を見ようといちじく桑の木に登りました。そこを通りがかったイエス様は上を見上げて「ザアカイ、急いで降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい」と言われました。ザアカイは、嬉しかったでしょう。有頂天。この嫌われ者の自分に、あのイエス様が話しかけて下さった。それも、自分の家に泊まって下さると。いつも自分が浴びている冷ややかな眼差しではなく、眼差しの何と優しいことか。「自分は神様に愛されている。イエス様、何日でもお泊り下さい。美味しい御馳走もお酒もあります。」そして、ザアカイは言いました。「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。また、だれかから何かだまし取っていたら、それを四倍にして返します。」彼は、法が要求している以上のことをしようと決心したのです。ザアカイは、イエス様から「今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は、失われたものを捜して救うために来たのである。」というお言葉を頂きました。幸いなるかな、徴税人ザアカイ。
この状況を見た人たちは皆つぶやきました。「あの人は罪深い男のところに行って宿をとった。」この中にはファリサイ派の人もたくさんいたでしょう。彼らは、イエス様が仰っている内容を全く理解することはできなかったと思います。しかし、イエス様がメシアであることには薄々気づいていたのではないでしょうか。何故なら、イエス様は、隈なく宣教され「権威ある者としてお教えになった」(マタイ7:29)からです。権威とは、神様の権威です。だから、神の民である彼らが気づかないはずはないんです。彼らは、神様を認めたくなかったのです。だから、イエス様を激しく攻撃したのです。あんな奴がメシアであるはずがない、彼らはかたくなになり、イエス様を完全に否定したのです。がんばる【自分】の正しさを神様に認めさせたかったのです。一方で、ザアカイが神様に愛されていることが羨ましくて仕方がないという一面もある。だから、「あの徴税人、罪人のくせに。それにイエスは何だ、罪人の家に泊まるなんて。俺たちはこんなにがんばって律法を研究し守っているのに。律法を何だと思っているんだ、イエス、絶対にゆるせん!」と言い放ってしまうのです。彼らは、イエス様を殺す機会を窺っていたのです。ギリギリギリギリ歯ぎしりしながら。イエス様とファリサイ派の人々との間には、激烈な対立があったのです。
「あなたの罪は赦された」幸いなるかな、罪深い女
ファリサイ派の人々は、律法を熱心に研究するんですね。しかし、イエス様は、ユダヤ人たちに次のように言われます。「あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書を研究している。ところが、聖書はわたしについて証しをするものだ。それなのに、あなたたちは、命を得るためにわたしのところへ来ようとしない。」(ヨハネによる福音書5:39-40)この御言葉は、このコラムを読まれている皆さんに対する招きでもあるのです。わたしのところへ来なさいと。この御言葉は、皆さんにとって重大な意味を持っています。お招きを感謝して頂くか、拒否するか。
徴税人は、少しでもイエス様の近くにという強烈な思いに導かれながら、イエス様のところへ来ました。ここで、イエス様のもとに来たもう一人の人を紹介します。その人は、「罪深い女」です。
ルカ7:36-50です。
さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持って来て、後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、自分に触れている女がだれで、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」と思った。(・・・イエス様とファリサイ派の人とのやり取りを経て・・・)だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、私に示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」そして、イエスは女に、「あなたの罪は赦された」と言われた。同席の人たちは、「罪まで赦すこの人は、いったい何者だろう」と考え始めた。イエスは女に、「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」と言われた。」(ルカ7:36-50)
罪深い女、売春婦でしょう。当時のユダヤ社会では、徴税人と並んで罪人の代表と思われていました。私は、この女性に底なしの苦悶と寂しさを感じます。いや、彼女には苦悶とか寂しささえ無かったかもしれません。虚無。底なしの淵に転落し、自分では到底這い上がることができないほどの怖ろしい深淵。罪とはそういうものです。だから、このお方だけ。イエス様のそばにいさせてほしい、その強烈な思いに導かれてイエス様のところへ来ました。「香油の入った石膏の壺を持って来て、後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った」のです。
ここはファリサイ派の人の家です。彼女は、露骨に罵られたでしょう。あらん限りの罵詈雑言を浴びせられたでしょう。しかし、彼女にはイエス様しか見えない、イエス様のもとに。そして、彼女は、イエス様から「あなたの罪は赦された」、「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」というお言葉を頂きます。幸いなるかな、罪深い女。
【自分】を捨て、狭い門から入る
ファリサイ派の人々は、自分の中に誇ることができるもの、自分を支えることができるものをたくさん持っています。自分はファリサイ派であるというプライド。がんばって律法を研究し守っているという自負、自信満々。しかし、律法を守っていないくせに「律法を知らないこの群衆は、呪われている」(ヨハネによる福音書7:49)と人を見下している。金輪際、【自分】を手放そうとしない人々。
イエス様は言われます。「狭い門から入りなさい」(マタイ7:13)「狭い門」と聞くと、皆さんは、難関校の「狭き門」を思い浮かべると思いますが、それとは全く異なります。難関校の狭き門は、努力してがんばって入ろうとします。一方、イエス様が言われる狭い門は、イエス様に至る門なのですが、換言すると、救いに至る門。この門は、努力やがんばりで入ることは絶対にできません!!いや、努力やがんばりは邪魔でしかないですね。だから、ファリサイ派の人々に対して、イエス様は「愚か者」(ルカ12:20)「偽善者」(マタイ6:5)と言われるのです。箸にも棒にもかからない連中なんです。プライドだの何だのと【自分】が肥大したまま、イエス様に至る門を通ることはできないということです。【自分】をがっちり抱えたまま、イエス様のところに行けるわけがないです。
一方の徴税人ザアカイや罪深い女をしっかりと見て下さい。自分の中に誇ることができるもの、自分を支えることのできるものを何も持っていない人々。努力やがんばりで救われようなどとは微塵も思っていないです。「このお方だけ!少しでもイエス様に近づきたい」という強烈な思いに導かれて、イエス様のところに来ました。イエス様の御言葉「自分の持ち物を一切捨てないならば、あなたがたのだれ一人としてわたしの弟子ではありえない。」(ルカ14:33)そのものですよね。もう一つ、イエス様の重要な御言葉「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。」(マルコ8:34)この「自分」は、【自分】です。正に「幸福なるかな、心の貧しき者。天国はその人のものなり。」(マタイ5:3、文語訳)ですね。「心の貧しき者」の群れ、これが教会なのです。徴税人ザアカイと罪深い女は、御国を目指す私の仲間。私もこの二人に励まされるようにして、イエス様のもとに行きます。少しでも近くに。心地よい歩み。いや、私は、主と一つにされている。「わたしは、キリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。」(ガラテヤの信徒への手紙2:19-20)主と一体、これが全てです。
罪人が戻ってきた、神様は楽しみ喜ばれる
上述したように、この頃、徴税人や罪人たちはイエス様を訪ねるようになっていたのです。ルカ15章の冒頭に「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と不平を言いだした。」」(ルカ15:1-2)とあります。イエス様は、罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしていたんですね。ルカ15章のテーマは、「一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある」(ルカ15:10)です。
罪をおかした放蕩息子が帰って来た時も父親(神様)は祝宴を催しました(ルカ15:11-32)。「食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。」静かな食事会というよりは飲めや歌えの大宴会。罪人が悔い改めて神様のもとに帰って来た、神様は大喜び、有頂天、嬉しくて仕方がないのです。ゼファニヤ書3:17にはこうあります。「主はお前のゆえに喜び楽しみ/愛によってお前を新たにし/お前のゆえに喜びの歌をもって楽しまれる。」私も徴税人ザアカイと罪深い女と一緒にこの大宴会に参加します。本当に楽しそうです。イエス様が中心におられる御国の祝宴。
「このお方だけ、このお方のもとに」と何故、思えるのか?
本コラム『死ぬこと、生きること(第10号)-救いは恵み:人間の努力やがんばりは、一切関係ない』には、まだまだ続きがあるのですが、あまりにも長くなりますので、今回はこの辺にしておきます。いくつかの疑問を積み残してしまいました。
ファリサイ派の人々とは違って、徴税人や罪深い女は、何故、「このお方だけ、このお方のもとに」と思えたのでしょうか? 「救いは恵み」と言うけれど「恵み」とは何でしょうか? 恵みとは、一言でいうと、主の十字架の死と復活による救いのことです。しかし、イエス様は、ある日突然、唐突に私たちの世に来られたわけではありません。では、なぜ、イエス様が、永遠の隔たりを越えて、私たちの世に来られたのでしょうか? 「恵み」とは、怖いくらいの深みのあるものですが、その「深み」とは何でしょうか? 罪人が帰って来た、なぜ、神様は楽しみ喜ばれるのでしょうか?
上記のいくつかの「?」については、『死ぬこと、生きること(第11号)』に書かせて頂きます。少し先になると思いますが、楽しみにお待ち下さい。
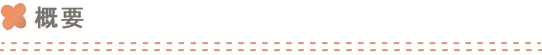
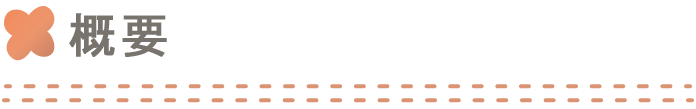
| 院長 | 吉田勝也 |
|---|---|
| 標榜科 | がん心療内科 |
| 資格 | 元日本緩和医療学会 緩和医療認定医 厚生労働省 精神保健指定医 日本医師会認定 産業医 |
| 住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢17-14 ユニバーサル南藤沢タワー403 |
| 申込用 メール アドレス |
gan-soudan@kzc.biglobe.ne.jp
電話番号は載せておりません 未掲載の理由はこちら |
| 連携医療機関 | 湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市民病院 |
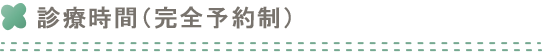

| 金曜日 | 13:00〜17:00(各50分〜4枠) |
|---|---|
| 土曜日 | 10:00〜15:00(各50分〜4枠) |
金曜日と土曜日が祝日と重なる場合は休診
1回50分という十分な時間をお取りして、心理療法的枠組みの中で、じっくりと相談して頂ける体制を整えています。
その体制を維持するために、すべて自費診療とさせて頂いています。健康保険は使えませんのでご留意ください。
