死ぬこと、生きること(第11号)-十字架の言葉は、救われる者には神の力
- TOP
- 死ぬこと、生きること(第11号)-十字架の言葉は、救われる者には神の力
死ぬこと、生きること(第11号)-十字架の言葉は、救われる者には神の力2025.04.20
「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です。」(コリントの信徒への手紙一1:18)
「神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されているからです。」(ローマの信徒への手紙1:17、聖書協会共同訳)
「十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていた」(コリントの信徒への手紙一2:2)
「わたしは、キリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。」(ガラテヤの信徒への手紙2:19-20)
低い所に下られるイエス様
今回は、『死ぬこと、生きること(第10号)-救いは恵み:人間の努力やがんばりは、一切関係ない』の続きです。登場人物は、「徴税人ザアカイ」(ルカ19:1-10)と「罪深い女(売春婦でしょう)」(ルカ7:36-50)でしたよね。彼らは、当時のユダヤ社会では、罪人の代表と思われており、激しく忌み嫌われ、誰からも相手にしてもらえませんでした。会堂(教会)からも完全に排除されていました。どうせ俺(私)なんか、無視され、顔を背けられ、嘲られ、救いから漏れている。彼らにはいつも軽蔑の眼差しが注がれていました。彼らが生活していたユダヤ社会は、ローマ帝国の支配下にあり、非常に閉鎖的でした。そして、ファリサイ派の人々が、宗教的社会的指導者として、幅を利かせていました。
ファリサイ派とは、「人に見てもらおうと、会堂や大通りの角に立って祈りたがる」(マタイ6:5)ような人々。お祈りは、本来、神様との親しい交わりのはずですが、彼らにとっては、あの人は敬虔で立派な人だ、と人に褒めてもらうための道具なのです。彼らは、律法を守っていない人を厳しく責め立てますが、自分は「言うだけで、実行しない」(マタイ23:3)のです。ザアカイや罪深い女も繰り返し激しく責め立てられたしょう。ファリサイ派の人々に対してイエス様は言われるのです。「愚か者」(ルカ12:20)、「偽善者」(マタイ6:5)、「蛇よ、蝮の子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか」(マタイ23:33)イエス様は、ファリサイ派のような人々を最もお嫌いになります。
このような社会の中で、ザアカイや罪深い女は、常に苦しめられていました。だから、社会に彼らの居場所は無かったのです。非常に生きづらかっただろうと思います。彼らは、神様の御前でも人の前でも、自分たちの罪を背負って生きてきたのです。自分で背負うにはあまりにも重い罪、自分の中のどこを見ても、この深淵から這い上がる術が何も無いという絶望。
しかし、イエス様は、低きに下って来られるお方です。ザアカイと罪深い女が落ちた限りなく深い深淵の底まで。「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。」(ヨハネ福音書1:14)「馬槽の中に産声上げ」と讃美歌にありますよね。馬槽(家畜の餌入れ)。イエス様は、家畜小屋で生まれられたのです。出生場所は、この世で最も低いところ。「宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである」(ルカ2:7)とあります。イエス様にも居場所が無かったのです。「人の子には枕する所もない」(マタイ8:20) そして、メシアであるイエス様は「人々から顔を背けられるほど軽蔑され」(イザヤ53:3、聖書協会共同訳)たのです。こんなこと、誰が信じられますか。でも、主は、正にザアカイや罪深い女と同じものになって下さったのです。「罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです。」(ヘブライ4:15) 神様の関心は、高い所ではなく、専ら低い所にあるのです。神は「世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。」(コリント一1:28)とあります。神様はこのようなお方です。私は、嬉しいです。ファリサイ派の人々はブツブツ呟き、イエス様に言うのです。「なぜ、あなたたちは、徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。」(ルカ5:30) 主はお答えになります。「医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。」(ルカ5:31-32)
遠くに、遠くに朧げに見える十字架
イエス様は、徴税人や罪人と飲食を共にされました。食事をし、酒を酌み交わしながら、他愛もない話に終始したのでしょうか。いや、それは非常に考えにくいです。イエス様は、寸暇を惜しんで至る所で宣教されるお方です。彼らにも噛んで含めるようにして、大切なことを話して聞かせたと思います。彼らは、主の御言葉を強烈に欲したでしょう。「主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇き」(アモス8:11)
「イエスが言われた。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが答えた。「神からのメシアです。」イエスは弟子たちを戒め、このことをだれにも話さないように命じて、次のように言われた。「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。」それから、イエスは皆に言われた。「わたしについて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、わたしのために命を失う者は、それを救うのである。」(ルカ9:20-24)
イエス様は、このようなたいへん大事なことを徴税人や罪人たちにも、飲食をしながら話して聞かせたと思うのです。一緒に食事をしようという主のお招きにおこたえした彼らに話さないはずはないでしょう。ペトロなど弟子たちはというと、「殺され、三日目に復活する」ことを理解できなかったのです(マタイ16:22)。そして、ザアカイや罪深い女はどうだったか…。やはり、よくわからなかっただろうと思います。しかし、彼らは、イエス様の御言葉の「殺される」「復活する」「自分を捨てる」「自分の十字架を背負う」が気になって仕方がないのです。何のことだろう…。食事が終わって家に帰って考え込むのです。このお方の御言葉を聞いているとき、何故だかわからないけど、嬉しかった、心が燃えていたではないか。「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」(ルカ24:32) そう思うとき、遠くに、遠くに朧げながらではあるけれども、イエス様の十字架が見えるような気がするのです。
イエス様は「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。」(マタイ11:28)と招いて下さっています。ザアカイと罪深い女は思うのです。遠くに、遠くに朧げに見える十字架を思いながら「ここには、私たちが神様と共に生きるための大切な何かがある。ここでなら、罪という重荷をおろすことができる。」彼らは、お招きにおこたえして、「このお方だけ、少しでもイエス様に近づきたい」という強烈な思いに導かれてイエス様のもとに来たのです。そんな彼らに対して、イエス様は、救いを宣言されます。罪深い女は、「あなたの信仰があなたを救った」というお言葉を頂きます。少しでもイエス様の近くに、このことを主は『信仰』と言って下さるのです。十字架の主のもとに来ることが『信仰』だとすると、十字架が指し示すものが何なのかを知りたいと思うでしょう。
以下、ザアカイと罪深い女が見た「遠くに、遠くに朧げに見える十字架」を追い求めていきたいと思います。でも、皆さん、イエス様の十字架が見えていますか。「このお方だけ、少しでもイエス様に近づきたい」という思いがありますか。パウロは、「目の前に、イエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。」(ガラテヤ3:1)と言っていますよ。
神様の【真実】から信仰へ
「あなたの信仰があなたを救った」、この御言葉を頂いた罪深い女は、本当に幸いと思います。しかし、この御言葉には悩ましい側面があるのです。私は、若いころ、この御言葉を聞くたびに不安になったのです。「あなたの信仰」とは「私の信仰」。主語は、私。私が、信じる。それは、私が行うこと?がんばって行うこと?若いころ、私はがんばって信じているようなところがありました。がんばって信じる、妙な表現ですが。力んでいましたね。救いは、努力やがんばりとは一切関係ないですから、力んでも駄目なんですね。だから、「私の信仰」なんて、ちょっとしたことで、グラグラ、ガタガタ、すぐにグラついてしまいます。どこに信仰があるのかと思うようなこともありました。こんな「私の信仰」で大丈夫なんだろうか、といつも思っていました。イエス様に「あなたの信仰」と言われると、時に、何か突き放されたような寂しさを感じることもありました。「主よ、そんなことを言わないで下さい。私の信仰を力強く支えて下さい。」ここでは、信じる、とはどのようなことなのか、がテーマになっています。
東京神学大学報(No330)に「日本伝道を担う青年の集い」の報告が掲載されていました。ある神学生が「『あなたの信仰があなたを救った』という主の御言葉は、自分にとって辛かった」と発言すると、ある牧師先生も若いころ、私もそうだった、と発言されています。私も「そうだそうだ」と大きく頷いていました。私と同じ辛さを経験したことがあるクリスチャンがいると思うとすごく嬉しいです。仲間がいた!
この悩みの解決は、当然ながら御言葉にあります。日本語訳の聖書にはいろいろありますが、2018年に『聖書協会共同訳』が出版されました。早速、購入して読みました。ガラテヤ2:16に「人が義とされるのは、律法の行いによるよるのではなく、ただイエス・キリストの真実による」とあります。あれっ、何か違うぞ、と思い、新共同訳を見ると「イエス・キリストへの信仰」となっています。えっ!と思いました。前者は、イエス様が主語、後者は、私の信仰ですから、私が主語です。翻訳によって、ベクトルの向きが180度違うのです。全身に電気が走るような衝撃を受けました。翻訳によって、理解が全く違ってきますよね、こんなのありですか、と思いました。細かい話をしているようですが、このことは、極めて重要です。
そして、すぐに気づいたのは、ローマ1:17もそうなっているよと。新共同訳「福音には、神の義が啓示されていますが、それは、初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。」、聖書協会共同訳「神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されているからです。」 前者は「初めから終わりまで信仰を通して」、後者は「真実により信仰へ」です。前者は、私の信仰を通して、と読めます。すぐにグラつく私の信仰が主語、不安で仕方がないです。
一方、聖書協会共同訳は、「真実により信仰へ」、「真実」は、ガラテヤを当てはめると、「イエス・キリストの真実」ですよね。「イエス・キリストの真実により信仰へ」です。カール・バルトは「神が真実によってあらわにするものは、信仰へとあらわにされる」と言っています。あっ、そうか、と思いました。元々、私には信仰なんか無いんですね。「私の信仰」ではないのです。先ずは、神様の、イエス様の真実があって、信仰が興されるのです。だから、ベクトルの向きは、私⇒神様ではなく、神様⇒私なのです。大本は、神様の【真実】なのです。【真実】から信仰へ、です。
神様の、イエス様の【真実】とは何でしょうか? 神様の【真実】は、私に何をして下さったのでしょうか? 具体的にみていきたいと思います。【真実】について、本当にわかるためには、神様と人間の関係に関する歴史を振り返らなくてはいけません。よって、私は、創世記の天地創造から始めたいのです。
天は、祝福と恵みの溢れんばかりの源泉
天地創造のお話の前に、エフェソ1:3-14の内容を是非とも押さえておきたいです。1:3-9を引用します。
「わたしたちの主イエス・キリストの父である神は、ほめたたえられますように。神は、わたしたちをキリストにおいて、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に、神はわたしたちを愛して、御自分の前で聖なる者、汚れのない者にしようと、キリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを、わたしたちがたたえるためです。わたしたちはこの御子において、その血によって贖われ、罪を赦されました。これは、神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みをわたしたちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画をわたしたちに知らせて下さいました。これは、前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。」
パウロは、何と力強く確信に満たされて語っているのだろうと思います。私たちは、天地創造の前に、イエス・キリストにおいて、選ばれたのだと。主の十字架の死と復活により、祝福され、神の子にされるために。そして、恵みはわたしたちの上にあふれるというのです。このことは、天の事実。天は、祝福と恵みの溢れんばかりの源泉なのです。永遠の命に至る水の源泉。汲んでも、汲んでも尽きない源泉。イエス様の御言葉「わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」(ヨハネ福音書4:14) この天の事実が、私たちの住む世にもたらされる救いの御業「秘められた計画」(1:9、コリント一4:1)の第一歩が、天地創造なのです。
では、神様による救いの目的は何でしょうか。「わたしたちの主イエス・キリストの父である神は、ほめたたえられますように」(1:3)と書かれています。私たち救われた者が、神様を礼拝するためです。「彼らは皆、わたしの名によって呼ばれる者。/わたしの栄光のために創造し/形づくり、完成した者。」(イザヤ43:7)
天地創造は、救いの御業の開始宣言
「初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり」(創世記1:1-2)
「地は混沌であって、闇が深淵の面にあり」というのです。「混沌」、口語訳では「形なく、むなしく」、新改訳では「茫漠として何もなかった」と訳されています。虚無であり、闇が深淵を覆っている世界。深淵とは、底なしの深み。そこに落ちたら二度と這い上がることができないのです。全てのものを飲み尽くし、滅ぼしてしまう罪の深み。あの徴税人ザアカイと罪深い女が落ちた深淵。闇がその深淵を覆っているというのです。どこに救いがあるのかと思わされます。
神様は、天地を創造されます。そのあと、「光あれ」(1:3)、「水の中に大空あれ。水と水を分けよ」(1:6)等々、次々と様々なものを造られます。人間を造るための準備です。神様が、活動を開始されました。人間を造るために。神様は、混沌と闇の世界において、人間と共に生きたい、と熱望されたのです。「初めに、神は天地を創造された」、この御言葉は、救いの御業の開始宣言であるのと同時に大きな慰めでもあるのです。
「わたし、わたしこそ神、あなたたちを慰めるもの。/なぜ、あなたは恐れるのか/死ぬべき人、草にも等しい人の子を。/なぜ、あなたは自分の造り主を忘れ/天を広げ、地の基を据えられた主を忘れ/滅びに向かう者のように/苦痛を与える者の怒りを/常に恐れてやまないのか。/苦痛を与える者の怒りはどこにあるのか。/かがみ込んでいる者は速やかに解き放たれ/もはや死ぬことも滅びることもなく/パンの欠けることもない。」(イザヤ51:12-14) 神様は、常に仰せられます。恐れるな!天地を創造し、あなたを造った「わたしに聞け」(イザヤ51:1)、わたしこそ神、あなたを慰めるものなんだよと。
命の息を吹き入れられ、生きる者となる
「神は御自分にかたどって人を創造された。/神にかたどって創造された。/男と女に創造された。/神は彼らを祝福して言われた。/「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。」」(創世記1:27-28)
「主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。」(創世記2:7)
神様は御自分にかたどって人を創造されました。そして、神様は、「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ」と人間を祝福されました。救いの御業は、祝福から始まったのです。
人間は、何で造られましたか。土の塵ですね。このことは、事実です。人間を構成している元素の組成を考えるとすぐにわかります。私たち人間は、塵の塊、生物に過ぎないということです。しかし、神様が人間の鼻に命の息を吹き入れられて、人は「生きる者となった」というのです。この生きるというのは、単に生物体として存在するということではありません。『死ぬこと、生きること(第9号)-死んでも生きる:【自分】は死に、新しく創造される』で「生物学的命とは異なる次元の命があります」と申し上げましたが、「生きる者」というのは、神様と共に生きる者、永遠の命を生きる者のことです。
ハイデルベルク信仰問答は、次のように言います。「神は、人間をよいもの、つまり、まことにご自身の姿に似せて、正しい聖いものにお造りになったのでありますから、人間は、神を自分の造り主として正しく知り、心から愛し、神とともに永遠の祝福の中に生き、神をほめたたえるようにして下さっているのであります。」
罪が支払う報酬は死です
「主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。/「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」/女は蛇に答えた。/「わたしたちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」/蛇は女に言った。/「決して死ぬことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。」/女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆していた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。」(創世記3:1-6)
上述したように、人間は、命の息を吹き入れられて、神様と共に生きる者、永遠の命を生きる者にして頂きました。しかし、です。人間は折角、神様の命を頂いたのに、捨ててしまったのです。どういうことか。人間は、神様から「園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから」と言われました。しかし、アダムは、有ろうことか「園の中央に生えている木の果実」を食べてしまったのです。神様の御言葉を捨てるという背き。「それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなる」とありますが、アダムは、神様を神様として礼拝するのではなく、【自分】が神になりたかったのです。【自分】の努力やがんばりを神様に認めさせたいのです。
この物語は、全ての人間が持っている、生まれながらの罪の姿を説明する物語です。これが、神様に背く【自分】、根源的な罪の全貌です(『死ぬこと、生きること(第7号)-根源的な罪:神様に背く【自分】』)。この【自分】は、ユダヤ人だけではありません。全ての人間の【自分】は、ユダヤ人と同じ【自分】なのです。
そして、園の中央に生えている木の果実を食べて、人間は死すべき者となりました。神様の命、永遠の命を捨ててしまったのですから。この時、「罪が支払う報酬は死です。」(ローマ6:23)が現実のものとなってしまったのです。この死は、単に生物学的に死ぬということだけではなく、滅びなのです。
死んで永遠に滅びる
滅びについて、聖書は次のように言います。「多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。/ある者は永遠の生命に入り/ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。(ダニエル12:2) 「永久に続く恥と憎悪」は、フランシスコ会聖書研究所訳では「永遠の恥とさげすみ」と訳されています。永遠の「恥」「憎悪」「さげすみ」、これらは、滅びの一つの形と思います。「主イエスは、燃え盛る火の中を来られ、神を知らない者や、私たちの主イエスの福音に聞き従わない者に、罰をお与えになります。彼らは、主の御顔から、またその御力の栄光から退けられ、永遠の滅びという裁きを受けるのです。」(テサロニケ二1:8-9、聖書協会共同訳)「永遠の滅び」とあります。命が永遠なら、滅びも永遠なのです。イエス様と一つにされて永遠の命を頂く人もいれば、神様に立ち帰ることなく永遠の滅びに定められる者もいる、ということです。
今、生きている私たちにとって、滅びには二つの側面があると思うのです。一つは、今、洗礼によってイエス様と一体にされていない人は、既に滅びを経験しています。意識する、しないに関わらず、死に支配されて苦しむという滅びの姿を日々曝しています。イエス様の御言葉「御子を信じる者は裁かれない。信じない者は既に裁かれている。神の独り子の名を信じていないからである。」(ヨハネ福音書3:18) もう一つは、死に際して、神様に見捨てられ、呪われた者として裁かれ、永遠に滅ぼされてしまいます。神様が共におられない死を死ぬのです。皆さん、神様が共におられない死を想像してみて下さい。ものすごく悲惨ですよ。神様を信じていない人でも、死ぬ時は、神様を求めてしまうんじゃないですか。死んで永遠に滅びてしまうから、死を前にして、後悔・罪悪感・罪の意識に激しく苛まれるのです。死に支配されて苦しむのです(『死ぬこと、生きること(第6号)-罪と死』)。「死んだら無になるだけ、だから別に怖くないよ」と言う人がおられますが、愈々死に直面すると、死んでも死にきれないという思いが溢れてくるのです。あなたひとりでは死ねないですよ。
神様は、全ての人間に「立ち帰れ!」と叫んでおられる
「二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はいちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。/その日、風の吹くころ、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。/「どこにいるのか。」」(創世記3:7-9)
アダムは、園の中央に生えている木の果実を食べて、神様に背きました。その時、アダムは、神様との関係は破綻してしまったと思ったでしょう。彼は、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れたのです。しかし、神様は、アダムを呼ばれるのです。「どこにいるのか」と。そして、聖書は言うのです。「主なる神は、アダムと女に皮の衣を作って着せられた」と。(創世記3:21) 神様は、尚も、アダム(人間)に配慮の目を向けられるのです。この配慮を具体的な言葉にすると「神様に立ち帰れ!」です。神様は、全ての人間に「神様に立ち帰れ!」と言って下さるのです。
偶像礼拝とは、【自分】を礼拝すること(「金の子牛」事件)
しかし、イスラエルの民は、とんでもないことをしでかすのです。モーセは、十戒を受け取るために、シナイ山に上っていたのですが、なかなか帰って来ません。彼らは、導き手を失うかもしれないという強い不安にかられ、待ちきれなくなり、新しい導き手を求めます。民はアロンに言うのです。「さあ、我々に先立って進む神々を造ってください。」(出エジプト32:1) アロンは、金の耳輪を集めて溶かし、若い雄牛の像を造りました。イスラエルの民は、驚くべき言葉でこの像を讃えたのです。「イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だ」(出エジプト32:4) 神様が、イスラエルの民を奴隷として暮らしていたエジプトから導き出して下さったにも関わらず、彼らは、金の子牛を造り、それにひれ伏し、犠牲をささげてしまったのです。忌むべき偶像礼拝です。偶像を拝むことによって、再び偶像の奴隷になり、偶像に支配されるようになりました。
皆さん、偶像とは何だと思われますか。ここでは、金の子牛。金の子牛を拝んだと。金の子牛は、神々の一つ。自分の思い通りになる目に見える神を造り、それに自分の思いや願いを投影し、それを拝むのです。だから、偶像礼拝というのは、神様を礼拝するのではなく、【自分】を礼拝しているのです。金の子牛は、象徴表現。お金や地位や他人の評価やあなたの所有物が神になっていることが多いですよね。それは、常に自分を他人と比較して上だの下だのという生き方に直接結びつきます。よい例が、ファリサイ派の人々ですね。努力したり、がんばったり、何かを為すことも。それらのものにしがみついて生きているのです(『死ぬこと、生きること(第10号)』。ありとあらゆるもの、何でもいいのです。私たちにとって偶像になり得ないものなど、この広い世界に存在するでしょうか。
私たちクリスチャンが毎週日曜日に礼拝している教会、非常に残念なことなのですが、教会とて例外ではありません。偶像が、神様の御言葉を聞くことや祈りを妨げていないでしょうか。イエス様の御言葉「こう書いてある。『わたしの家は、祈りの家と呼ばれるべきである。』ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にしている。」(マタイ21:13) 教会が、御言葉や祈りを奪う『強盗』の巣窟になっていませんか。ファリサイ的なクリスチャンが、妨げになっていませんか。徴税人ザアカイや罪深い女のような人々を教会から締め出していませんか。あなたの教会は大丈夫ですか。
そして、すべての偶像の中でも最もかたくなな偶像は、様々な欲求や習慣を持ち、こころと気分がすぐに変わってしまう【自分】なのです。偶像礼拝とは、【自分】を金輪際手放さない生き方そのものです。
「金の子牛」事件で、イスラエルの民は、2つの十戒を破っています。聖書協会共同訳から引用します。第1戒、「あなたには、私をおいてほかに神々があってはならない。」(出エジプト20:3) 第2戒、「あなたは自分のために彫像を造ってはならない。」(出エジプト20:4) 第1戒と第2戒を読むとき、私は、イエス様の重要な御言葉「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。」(マルコ8:34)を強くイメージします。この御言葉の「自分」は、【自分】です。
知らないうちに永遠の滅びに定められている
「生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神、主を愛し、御声を聞き、主につき従いなさい。」(申命記30:19-20)
死(永遠の滅び)ではなく生(永遠の命)を、呪いではなく祝福を選びなさい。この御言葉は、全ての人間にとっての神様からの招きです。全ての人間ですから、もちろん、あなたも含まれますよ。あなたのこと!です。この招きを感謝して頂くのか、拒否して捨ててしまうのか、皆さんは、重大な岐路に立っています。一方は、死(永遠の滅び)と呪いへの道、もう一方は、生(永遠の命)と祝福への道です。今、あなたは、どの道にいますか。永遠の滅びや呪いへの道にいるということには、なかなか気づけないものなのです。極めて多くの人は、知らないうちにその道に迷い込んでいます。死に直面しても気づかない人が非常に多いですね。本当に怖いことです。しっかりと御言葉に聞いて、気づいて頂きたいと思います。「わたしこそ主、わたしの前に神は造られず/わたしの後にも存在しないことを。/わたし、わたしが主である。/わたしのほかに救い主はない。」(イザヤ43:10-11)「ほかのだれによっても、救いは得られません。わたしたちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。」(使徒言行録4:12)
イスラエルの民は、永遠の滅びを選んだ
イスラエルの民は、重大な岐路に立って、どのような道を選んだのでしょうか。
「奪う者にヤコブを渡し/略奪する者にイスラエルを渡したのは誰か。/それは主ではないか/この方にわたしたちも罪を犯した。/彼らは主の道に歩もうとせず/その教えに聞き従おうとしなかった。/主は燃える怒りを注ぎ出し/激しい戦いを挑まれた。/その炎に囲まれても、悟る者はなく/火が自分に燃え移っても、気づく者はなかった。」(イザヤ42:24-25)
「主よ、御目は/真実を求めておられるではありませんか。/彼らを打たれても、彼らは痛みを覚えず/彼らを打ちのめされても/彼らは懲らしめを受け入れず/その顔を岩よりも固くして/立ち帰ることを拒みました。」(エレミヤ5:3)
神様は、常に「わたしに聞け」(イザヤ51:1)、「背信の子らよ、立ち帰れ」(エレミヤ3:14)と呼びかけて下さっています。それにも関わらず、炎に囲まれても、火が自分に燃え移っても、悟らない、気づかない。打たれても、痛みを覚えない。懲らしめを受け入れず、立ち帰ることを拒んだ。イスラエルの民は、神様と共に生きようとはしませんでした。彼らは、神様によって選ばれた特別な民であるにも関わらず、御言葉に耳を傾けず、神様に背いて生きているのです。このようなユダヤ人の極度のかたくなさが、イエス様を完全に否定して、十字架にかけて殺してしまったのです。
このかたくなさは、ユダヤ人だけのものではないです。私たちもそうです。人種、民族を問わず、人間の本質は同じです。イザヤ書やエレミヤ書に描かれているこの極度のかたくなさは、正に私たちのものです。どんなに悲惨な状態に陥っても、何も気づかない私たちなのです。上述した通り、知らないうちに永遠の滅びに定められています。だから、死に直面して苦しむのです(『死ぬこと、生きること(第6号)-罪と死』)。
神様の燃える怒りとバビロン捕囚
これらの御言葉が示す通り、イスラエルの民は、死(永遠の滅び)と呪いへの道を選んでしまいました。聖書は、死(永遠の滅び)は、神様の「燃える怒り」によるのだと言います。イスラエルの民の極度のかたくなさのために、彼らにとっての最悪の出来事が起こりました。バビロン捕囚です。紀元前587年、エルサレムは、バビロンによって徹底的に滅ぼされました。神殿は焼き払われ、イスラエルの民は、捕囚としてバビロンへと連れ去られたのです。
神様の「燃える怒り」。神は愛と聞いたことがあるが、神の怒りとは何だ、と思われている人はたいへん多いと思います。こんな言葉を聞くとすごく怖いと思います。私はといえば、全く怖くないです。私は、イエス様と一体であり、「命をもたらす霊の法則」(ローマ8:2)の中に入れられていますから。
私たち人間の怒りは、【自分】を押し通すために発せられます。【自分】が【自分】が、の怒りです。よって、神様の怒りを私たち人間の知識や経験の範囲で考えますと、大きな間違いをしてしまいます。主の十字架の光で、神様の怒りを照らしましょう。神様の怒りを抜きにして、神様の愛や主の十字架による救いは、わからないと思うのです。
「私は正しい人間」と言い張ることが、罪の姿そのもの
「「立ち帰れ、イスラエルよ」と/主は言われる。」(エレミヤ4:1) 神様は、イスラエルの民に、何度も何度も、立ち帰れ、と言って下さったにも関わらず、神様を拒みました。その結果が、バビロン捕囚です。「わたしは見た。/見よ、大地は混沌とし/空には光がなかった。」(エレミヤ4:23) イスラエルの民は、絶望し、生きる意味を失いました。
それでも、神様は、私たち人間と共に歩みたい、立ち帰れ、と叫んでおられます。神様は決して諦めることをなさいません。しかし、神様のお招きにも関わらず、イスラエルの民は、かたくなになって、神様のお招きを拒否し続けるのです。だから、「主の激しい怒りは我々を去らない」(エレミヤ4:8)のです。「それゆえ、主はその民に対して怒りを発し/御手を伸ばし、彼らを打たれた。/山々は震え、彼らの死体は通りの真ん中に/ごみのように横たわっている。/それでもなお、主の怒りは去らず/その手は伸ばされたままだ。(イザヤ5:25、聖書協会共同訳)
「主の激しい怒り」、「燃える怒り」は、イスラエルの民に向けられています。同時に、皆さんにも向けられているのです。皆さんは、ここをどのように読まれますか。神様の怒りは、あなたには関係ないですか。
「不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを現されます。」(ローマ1:18) 彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため、彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、ねたみ、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事をたくらみ、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らは、このようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。(ローマ1:28-31)
これらのどれも身に覚えがないという方はおられますか。誰でも一つや二つや三つ……は、思い当たるんじゃないですか。聖書には「義人なし、一人だになし」(ローマ3:10、文語訳)とあります。神様の前では、正しい人など一人もいないのです。中には「自分には罪なんかありません」と言い切ってしまう人もおられるようですが、イエス様は、ファリサイ派の人々に次のように言います。「もしあなたがたが盲人であったなら、罪はなかったであろう。しかし、今あなたがたが『見える』と言い張るところに、あなたがたの罪がある。」(ヨハネ福音書9:41、口語訳) 「私には罪なんかない、正しい人間なんだ」とかたくなに言い張ることが、罪の姿そのものなのです。
神様の怒りのないところには、十字架もあり得ない
神様の怒りに関して、リュティは、「この世の悪に対して、最後の血の一滴まで戦うお方が一人だけある。それが神である」と言います。人間一人一人を見ても、社会の中を見ても、世界的な視野に立っても、何でこんなことが、と思うような悲惨なことがたくさん起こっていますが、この世の悪に対して、最後の血の一滴まで戦われる神様がおられるというのは、大きな慰めです。「わたしは瞬く間に/わたしの裁きをすべての人の光として輝かす。」(イザヤ51:4) イエス様は言われます。「まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。」(ルカ18:7-8)
バークレーは、ある学者の「神は神である故、また本質的に聖なるが故に、罪を黙許することができない。神の怒りは、罪に対する神の「根絶的反動」である」を引用して、次のように言います。「このことはわれわれにとって理解し、容認することがはなはだ困難である。事実、このことは旧約聖書の宗教とかかわりをもったものであって、新約聖書の思想ではないからである。」さらに、バークレーは、宗教改革者ルターについて、「彼でさえもこのことが理解に困難であることに気づいている。彼は神の愛を神自らの働きとして語り、神の怒りを神の特殊な働きとして語った。それはキリスト者の知性にとって不可能なことだからである」と述べます。
しかし、です。私は、バークレーとルターの考えには、大きな違和感を覚えます。神様の怒りは、旧約聖書の宗教とかかわりをもったものであって、新約聖書の思想ではないとか、それは、神の特殊な働きとか、そのように考えてしまいますと、イエス様の十字架を見くびり、恵みを小さなものにしてしまうと思うのです。「十字架の言葉は、神の力」なのですから。よって、私は、神様の怒りが、神の特殊な働きとは思いません。神様の愛がそうであるように、神様の怒りも神自らの働きです。私は、神様から「罪を犯した魂は必ず死ぬ。」(エゼキエル18:4、口語訳)、永遠の滅びに定められている、と言い渡されたにも関わらず、主の十字架により「罪と死との法則」から解放され「命をもたらす霊の法則」(ローマ8:2)に入れて頂きましたからよくわかるのです。神様の怒りと愛は、一つなのです。神様の怒りのないところには、十字架もあり得ないと思うのです。
神様の激しい怒りは、イエス様の頭上で炸裂した
上記のことと関連しますが、こんなことを言っている人がいました。「旧約聖書の神様は、厳しいから嫌いなんですが、新約聖書の神様は、優しいから好きです。」ちょっと待って下さい。旧約聖書の神様と新約聖書の神様は、同じですから(父なる神様)。怒りの神様を自分から切り離したいんですね。でも、新約聖書にも厳しいことが書かれています。「御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は、命にあずかることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。」(ヨハネ福音書3:36) パウロは言います。「何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。」(フィリピ3:18-19) そして、イエス様は次のように言われます。「わたしにつながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして、集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。」(ヨハネ福音書15:6) 裁きですね。イエス様も厳しいですよ。でも、私はこんなイエス様が大好きです。
神様の怒りということで申し上げますと、これは、極めて重要なことですが、神様の燃えるような激しい怒りは、罪に引きずり回されている私たち人間ではなく、父なる神の御子であるイエス様の頭上で炸裂したのです。だからこう言えるのです。「わたしは背く彼らをいやし/喜んで彼らを愛する。/まことに、わたしの怒りは彼らを離れ去った。(ホセア14:5) 「神は、わたしたちを怒りに定められたのではなく、わたしたちの主イエス・キリストによる救いにあずからせるように定められたのです。主は、わたしたちのために死なれましたが、それは、わたしたちが、目覚めていても眠っていても、主と共に生きるようになるためです。」(テサロニケ一5:9-10)
新しい契約:神の子イエス・キリストの福音の初め(マルコ1:1)
「見よ、わたしがイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この契約は、かつてわたしが彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない。わたしが彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし、来るべき日に、私はイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。そのとき、人々は隣人どうし、兄弟どうし、「主を知れ」と言って教えることはない。彼らはすべて、小さい者も大きい者もわたしを知るからである、と主は言われる。わたしは彼らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留めることなない。(エレミヤ31:31-34)
「新しい契約」、神様は、イエス様を私たちの世に遣わすという、全く新しいことを始められました。神様は、人間を救うための最終手段に打って出られたのです。人間にとっては、最後のチャンスということです。後がありません。「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。(ヨハネ福音書3:16) 神の子イエス・キリストの福音の初め(マルコ1:1) イエス様は言われます。「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」(マルコ1:15) 永遠の隔たりを越えて、イエス様がこの世に来て下さったのです。
「あなたは永遠に滅びる」と言われたその場所で、「あなたは神の子」と呼ばれる
『死ぬこと、生きること(第8号)-イエス様の十字架の死と復活は、私のためであった!』で、イースターの日に、私が見た夢のお話をしました。この夢によって、神様は、私をどのように見られているかがはっきりとわかりました。「見よ、主の日が来る/残忍な、怒りと憤りの日が。/大地を荒廃させ/そこから罪人を絶つために。」(イザヤ13:9) 「残忍な、怒りと憤りの日」、「主の激しい怒り」、「燃える怒り」は、イスラエルの民に向けられています。同時に、神様の燃えるような激しい怒りは、間違いなく私に向けられていたのです。
「罪を犯した魂は必ず死ぬ。」(エゼキエル18:4、口語訳) 私は、神様のこの御言葉を確かに聞いたのです。「あなたは、死ななければならない。そして、永遠の滅びに定められている」朝、目が覚めたとき、私は絶望しました。これで終わり、と思いました。今、この時のことを振り返っています。「あなたは、死んで永遠に滅びる」この神様の御言葉に対して、私には、何の文句・反論もありません。私は唯こう言うだけです。「主よ、あなたの前では、私は最悪の罪人です。裁かれて当然です。」「わたしは、その罪人の中で最たる者です。」(テモテ一1:15) そして、あの徴税人が祈ったように私も「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」(ルカ18:13)と祈ります。
最悪の罪人とわかったときは、私には絶望しかありませんでした。神様の怒りによって、徹底的に滅ぼされると思いました。しかし、です。神様の燃えるような激しい怒りは、罪に引きずり回されている私ではなく、父なる神の御子であるイエス様の頭上で炸裂したのです。この瞬間、次の御言葉が私に実現したのです。「「あなたたちは、ロ・アンミ(わが民でない者)」と言われるかわりに/「生ける神の子ら」と言われるようになる。」(ホセア2:1)
そして、イエス様の十字架上での御言葉「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」(マルコ15:34) メシアであられるイエス様の御姿「彼には見るべき麗しさも輝きもなく/望ましい容姿もない。/彼は軽蔑され、人々に見捨てられ/痛みの人で、病を知っていた。人々から顔を背けられるほど軽蔑され/私たちも彼を尊ばなかった。」(イザヤ53:2-3、聖書協会共同訳) 「私たちが聞いたことを、誰が信じただろうか。」(イザヤ53:1)ですよね。イエス様は、十字架上で、私の罪、すなわち、私の全てを背負い、神様から見捨てられ、呪われた者として、私の身代わりとして、死んで、永遠に滅んでしまわれたのです。そして、三日目に、死を打ち破り、永遠の滅びから復活されたのです。「彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し/背く者の一人に数えられたからだ。/多くの人の罪を担い/背く者のために執り成しをしたのは/この人であった。」(イザヤ53:12、聖書協会共同訳) 私の罪を担い、私のために執り成しをしたのは、イエス様です。
死も復活もイエス様と同じ状態になる
「わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちも新しい命に生きるためなのです。もし、わたしたちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。」(ローマ6:4-5)
神様の燃えるような怒りは、私ではなく!十字架上のイエス様の頭上で炸裂しました。その時、私はどこにいたのか。イエス様と共に十字架につけられていました、聖霊により時間と空間を超えて、です。この時「わたしは、キリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。」(ガラテヤ2:19-20)が、私に実現したのです。十字架上で、私はイエス様と一体にされたのです。洗礼とは、イエス様と一体になって、全てを共にすることなのです。主と一体にならない洗礼などどこにあるのでしょうか。何と恵みに満ちているのだろうと思います。「恵みは海の波のようになる。」(イザヤ48:18)「神はこの恵みをわたしの上にあふれさせ」(エフェソ1:8) 「そして、わたしたちの主の恵みが、キリスト・イエスによる信仰と愛と共に、あふれるほど与えられました。」(テモテ一1:14)「神は、独り子を世にお遣わしになりました。その方によって、わたしたちが生きるようになるためです。ここに、神の愛がわたしたちの内に示されました。」(ヨハネの手紙一4:9)
「洗礼によってキリストと共に葬られ」(6:4) 私は、イエス様と共に葬られました。「葬られ」、使徒信条には「死にて葬られ、陰府にくだり」とあり、極めて重要なことを意味しています。私は、イエス様と共に死んで墓に葬られました。そして、イエス様が私を抱きかかえるようにして、永遠の滅びまで連れていって下さいました(「陰府にくだり」)。陰府といっても、イエス様と共にですから大丈夫なのです。私が、主と共に永遠の滅びを経験することが極めて大事なのです。アダムの命、即ち罪に引きずり回されている古い自分が、確実に完全に死ぬことが大事なのです。その確実性・完全性は徹底しています。「恵みの絞殺」「人間に対して備えた埋葬の真剣さ、エネルギー、ラディカリズム」(カール・バルト)。イエス様は、私を抱きかかえるようにして、永遠の滅びまで連れて行って下さり、そして復活されました。復活までも私を伴って下さったのです。「わたしたちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。」(6:5)とある通りです。聖書協会共同訳では「私たちがキリストの死と同じ状態になったとすれば、復活についても同じ状態になるでしょう。」と訳されています。死も復活もイエス様と同じ状態になるのです。新しい死と命の発見。こんな死があったのか!こんな命があったのか!「イエスは言われた。「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。このことを信じるか。」」(ヨハネ福音書11:25-26)
イエス様の十字架上で、神様の怒りと愛は一つになる
主の十字架の事実、一つは、神様の怒りは、イエス様の頭上で炸裂したこと、もう一つは、神様の愛は、私の内に示されことです。この二つのことが同時に起きたのです。もともと神様の怒りと愛は、一つのものですが、私たち人間には、二つのものに見えてしまいます。しかし、主の十字架上で、神様の怒りと愛は一つになり、私が、イエス様と共に死んで葬られ、陰府にくだり、そして、復活するプロセスを実現せしめるのです。正に「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です。」(コリントの信徒への手紙一1:18) 私は言います。「主よ、全くその通りです。ありがとうございます。」だから、私は「十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていた」(コリントの信徒への手紙一2:2)という御言葉を噛み締めるのです。
カール・バルトは次のように言います。「復活の力において、「父の栄光によって死者の中からよみがえらされる」ことにおいて(人間にとって不可能なことが可能になることにおいて)現実的否定、すなわちキリストが、この人間に対して備えた埋葬の真剣さ、エネルギー、ラディカリズムが実証され、裏付けられて、さらに新しい、不可視的人間の創造において、遂行された和解の真理(ローマ5:10-11)が、またキリストにあるわれわれの存在において、アダムにあるわれわれの存在の廃棄が、実証され、裏付けられるからである。」「新しい、不可視的人間の創造」、「だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者なのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」(コリント二5:17) 「従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。キリスト・イエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。」(ローマ8:1-2)
信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら
今や、徴税人ザアカイと罪深い女が、遠くに、遠くに朧げに見たであろう十字架は、私たちの目の前に、はっきりと示されました。聖書には「目の前に、イエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。」(ガラテヤ3:1)とあります。皆さんも十字架がはっきりと見えていますよね。神様の【真実】を追い求めて、ここまで来ました。神様は、御自分の【真実】を、神様の怒りと愛の会えるイエス様の十字架において示して下さいました。「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です。」(コリント一1:18)
私は、神様の【真実】とは、天地創造から主の十字架、そして御国に至るまでの全てと思うのです。どんなことがあろうとも、神様が人間と常に関り続けて下さっているのですから。その歴史の重みを味わいたいのです。神様の【真実】、一言にすると「私をイエス様と一体にし、私の罪をゆるし、神の国まで豊かに導いて下さること」です。「ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなたがたから離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになる。」(使徒言行録1:11) 「わたしたちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、わたしたちは待っています。」(フィリピ3:20) 「以上すべてを証しする方が、言われる。「然り、わたしはすぐに来る。」アーメン、主イエスよ、来てください。」(ヨハネの黙示録22:20) 「見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。」(ヨハネの黙示録21:3-4)
「神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されているからです。」(ローマ1:17、聖書協会共同訳) イエス様は、罪深い女に「あなたの信仰があなたを救った」(ルカ7:50)と言われました。「あなた(私)の信仰」の前提に、神様の【真実】があるのです「真実により信仰へ」。神様は、私たちに【真実】を示して下さいました。だから、ザアカイや罪深い女のように、神様の【真実】だけを見て、「もう、このお方だけ、少しでも主に近づきたい」という強い思いに導かれて、イエス様のもとに行くのです。主は、このことを「あなた(私)の信仰」と認めて下さるのです。「信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら」(ヘブライ12:2)復活の主(「屠られたような子羊」ヨハネの黙示録5:6)のもとに行くのです。主と一体とされた者は、他者も自分をも見ることなく、イエス様だけを見つめる者とされたのです。「一筋の心」(詩編86:11)を主に向けるのです。そして、主の【真実】を感謝して頂いて、イエス様のもとに行く、ただ、それだけでよいのです。「私にとって、生きることはキリストであり、死ぬことは益なのです。」(フィリピ1:21、聖書協会共同訳) ハイデルベルク信仰問答 「(問1)生きている時も、死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは、何ですか。(答)わたしが、身も魂も、生きている時も、死ぬ時も、わたしのものではなく、わたしの真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。」「だから、体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれる者でありたい。」(コリント二5:9)
神様は「あなた(私)の信仰」に責任を負って下さる
そうは言っても、皆さん、まだ不安がありますよね。祈れなくなったらどうしよう。病気で意識が無くなったら、認知症になっていろいろなことがわからなくなったら、神様の【真実】を感謝して頂いて、主のもとに行くことができなくなるではないか、と思いますよね。でも、問題なし!です。イエス様と一体にされているのですから。以上。でも、もう少し具体的にみていきたいですよね。
「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。この方は、真理の霊である。」(ヨハネ福音書14:16-17) 聖霊なる神様が、永遠に私たちと一緒にいて下さるというのです。永遠にというのは、何があっても永遠に、ということです。祈ることができないから、病気で意識がないから、認知症でわからなくなったから引き揚げます、は絶対にないのです。「弁護者、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊が、あなたがたにすべてのことを教え、わたしが話したことをことごとく思い起こさせてくださる。」(ヨハネ福音書14:26) 聖霊なる神様とは、このようなお方なのです。
そして、パウロは、「執り成し」を強調します。まずは、聖霊なる神様の執り成しについて。「同様に、”霊”も弱いわたしたちを助けてくださいます。わたしたちはどう祈るべきかを知りませんが、”霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り成してくださるからです。」(ローマ8:26) 次にイエス様の執り成しについて。「死んだ方、否、むしろ、復活させられた方であるキリスト・イエスが、神の右に座っていて、わたしたちのために執り成してくださるのです。」(ローマ8:34) それに、イエス様は、「あなた(私)の信仰」を祈りによって支えて下さっています。主は言われます。「しかし、わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。」(ルカ22:32) イエス様が、私のために祈って下さっているのです。嬉しいですね。だから、もう何の心配もいらないですね。主は、私の信仰を支え、導き、責任を負って下さるのです。祈れなくなっても、意識が無くなっても、認知症になってわからなくなっても安心です。そして、パウロの確信、「死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高い所にいるものも、低い所にいるものも、他のどんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです。」(ローマ8:38-39) 一度、十字架上でイエス様と一体にされたら、「どんな被造物も、わたしたちの主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことはできないのです。」
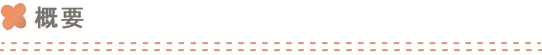
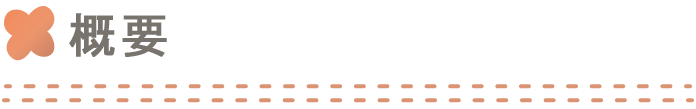
| 院長 | 吉田勝也 |
|---|---|
| 標榜科 | がん心療内科 |
| 資格 | 元日本緩和医療学会 緩和医療認定医 厚生労働省 精神保健指定医 日本医師会認定 産業医 |
| 住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢17-14 ユニバーサル南藤沢タワー403 |
| 申込用 メール アドレス |
gan-soudan@kzc.biglobe.ne.jp
電話番号は載せておりません 未掲載の理由はこちら |
| 連携医療機関 | 湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市民病院 |
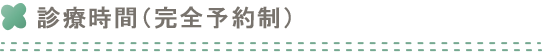

| 金曜日 | 13:00〜17:00(各50分〜4枠) |
|---|---|
| 土曜日 | 10:00〜15:00(各50分〜4枠) |
金曜日と土曜日が祝日と重なる場合は休診
1回50分という十分な時間をお取りして、心理療法的枠組みの中で、じっくりと相談して頂ける体制を整えています。
その体制を維持するために、すべて自費診療とさせて頂いています。健康保険は使えませんのでご留意ください。
